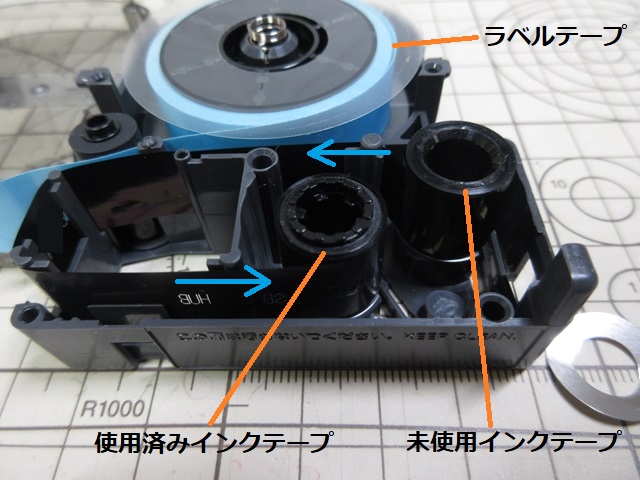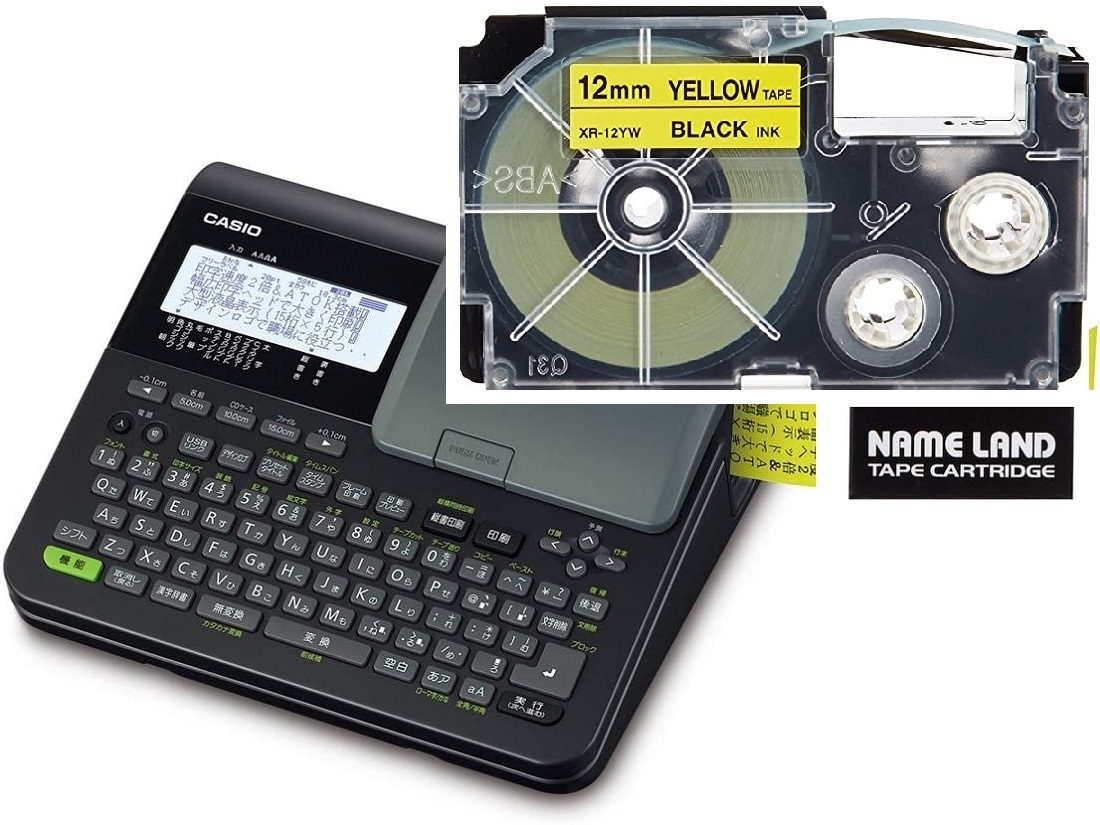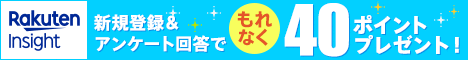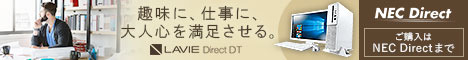ちぎれた 『ネームランドテープ』繋いで修理│その手順
CASIOの人気ラベルプリンター ネームランド 。
新品のうちはいいのだけれど、保管が長いと?ラベルテープが切れることがある。
でも切れたからと毎回買い替えていてはやっぱり勿体ない。
そんな時は『ネームランドのテープを繋ぎ直す』ことにしている。
CASIOラベルテープの修理
1 テープのしくみ
CASIO ネームランドでもKINGJIM テプラでも “ラベルテープ” の仕組みは同じような感じで、だいたい3層になっている。
【CASIOネームランドのカートリッジ 】
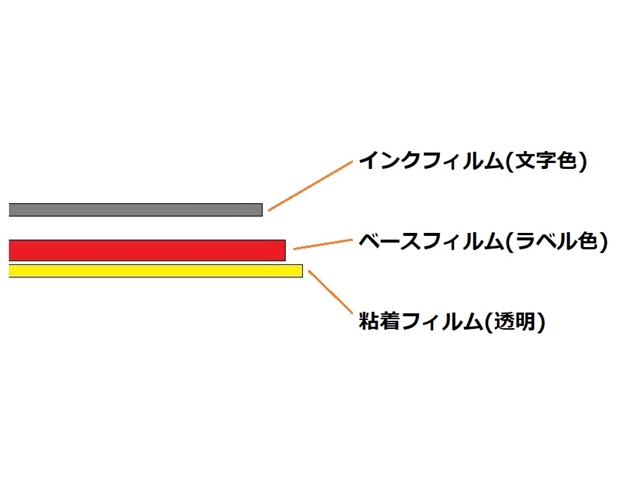
3層の例
カートリッジを選ぶ時、
「何色の文字がいいかな」
と悩む部分がインクフィルム
(赤や白など文字の色)
「何色のテープがいいかな」
と悩む部分がベースフィルム
(黒や透明などラベルの色)
2 カートリッジの構造
カートリッジ内を観察するとテープが巻かれた“3つのリール”が見える。
左の大きなリール にはベースフィルム+粘着フィルムが一重で巻かれている。
下の小さなリール にはプリント前のインクフィルム巻かれている。
右の小さなリール には使用済みインクフィルムが巻き取られる。
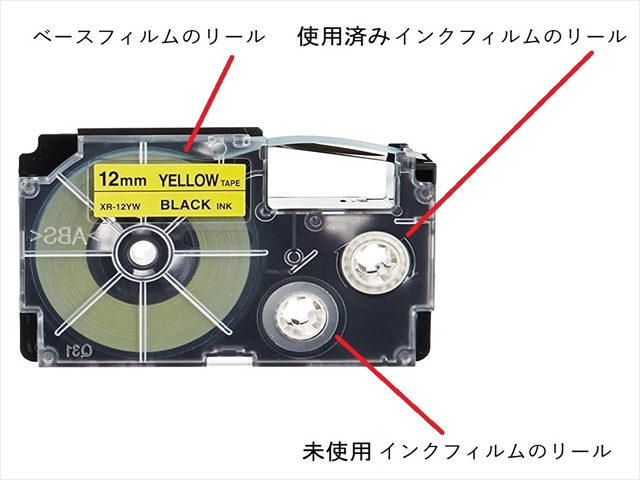
プリントアウトされたラベルは、3層が重なり1枚になって出てくる仕組み。
3 テープ切れの理由
問題が起きやすいのはインクフィルムである。
ラベルプリンターのどこかが調子悪いと ⇒ 未使用リールの送り出しと使用済みリールの巻き取りがうまく噛み合わなくなり ⇒ インクテープに負荷がかかって ⇒ 切れてしまう。
それがカートリッジの中で起こるから始末が悪い。
テープが切れたからと言って、いちいち本体とカートリッジを一緒に修理に出すわけにもいかず、結局しぶしぶ買いなおすことになる。
なぜインクフィルムが切れやすいのか?
その理由は “一番薄いから” 。
例えるのが難しが、文房具にあるまっ黒なカーボン紙に近いかも?
あれをもっと薄くしたような ペラッぺら のフィルムなのである。
修理はこの薄~いフォルムをつなぐことになる。


4 修理手順
1. カートリッジを観察
分解する前に「切れたテープの端と端がどこにあるか」を確認。
たいていは片方がカートリッジの外(印字部分)、もう片方がカートリッジの中。

2. カートリッジを分解する
作業にはピンセットと、先の細いマイナスドライバーがあると便利。
カートリッジケースにネジ類は使われておらず、はめ込まれているだけ。
なので、マイナス(-)ドライバー等でケースの隙間を探って、こじ開ける。

このカートリッジの場合は下面側の中央と側面に差し込めた。
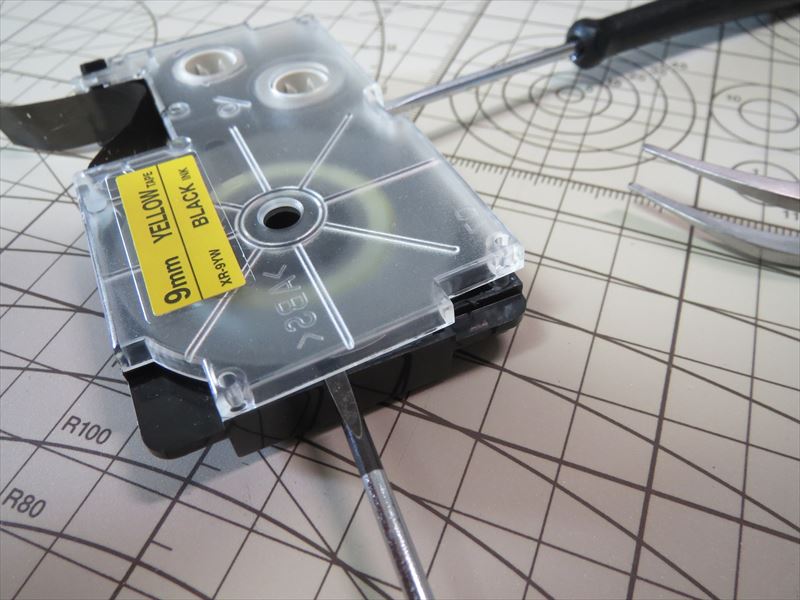
マイナスドライバを2本使って少しずつ開いた隙間を広げていく。
ネジは使われていないが、所々に接着剤らしき痕跡(白いあと)が見える。
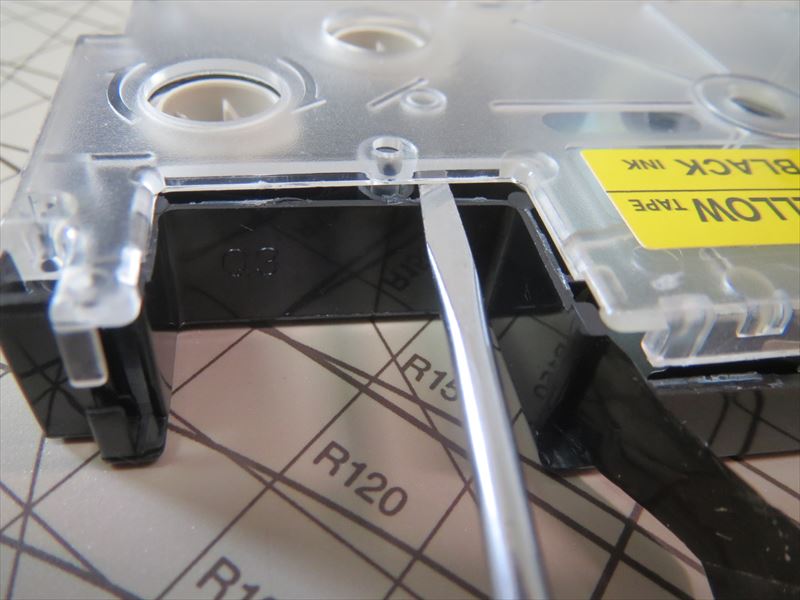
この接着個所をマイナスドライバーではがしていく。
ケースを割らないよう慎重に。
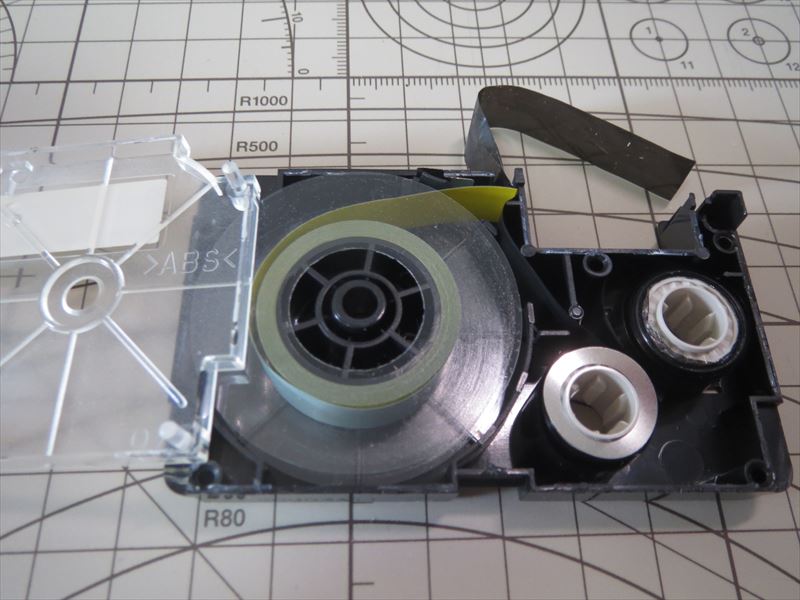
3. 切れたテープの両端を引き出す
切れたテープをまずは観察。
修理するテープの両端を、そっと慎重に引き出す。
長めに引き出したほうが作業性がいい。
写真⇩ 使用済みインクテープを見ると作った文字がバレバレ(w
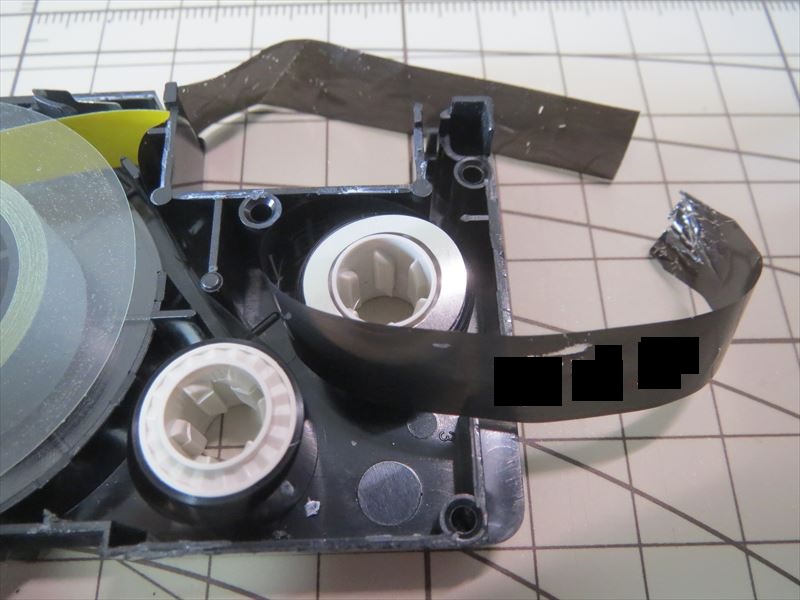
4. テープ両端を揃えてテープで貼る
手順は以下の通り。
- 接着力の弱いテープ(マスキングテープ等)を用意
- 切れたインクテープの両端をあえて少し重ねるようにして一直線に並べる
- 一直線になったインクテープをマスキングテープ等で仮止めする
- 少し重ねたインクテープ部分を一緒にカットして断面を揃える
- 不要なカット破片を取り除く
- インクテープ突き合わせの境目に”透明テープ”を貼ってつなぐ
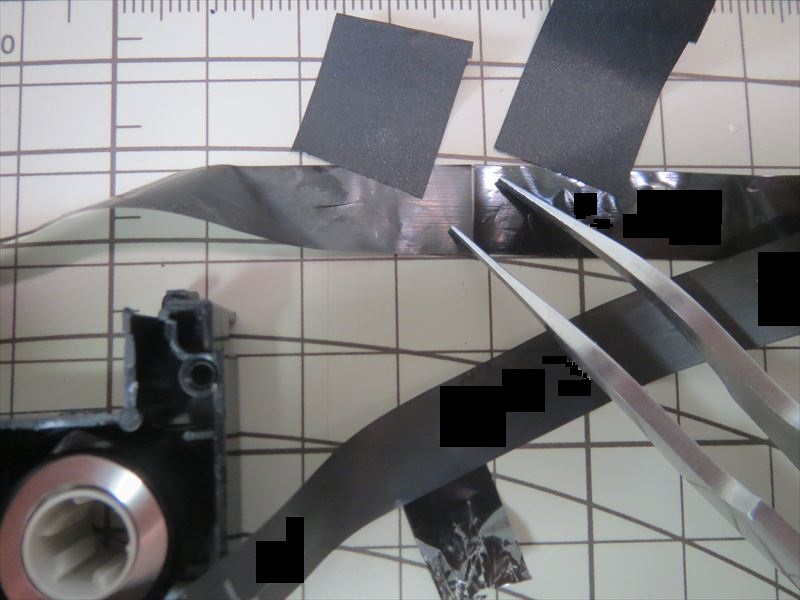
修理に使う”透明テープはなるべく薄い方が良い。
一般的なセロテープなどは厚みが0.050mm。
3M製『スコッチ超透明テープS』の厚みは0.045mm。
もっと薄手の0.023mm厚の商品もある。
こちら薄く柔らかく仕上がりは上々なテープ。
修理の時、繋ぎ合わせテープをやり直そうと剥がしでもたら1発で破れる。
この薄さが結構やっかいなのである。
補修のテープ貼りは一発勝負。
テープ貼りに失敗するとやり直しは不可能なので、その部分は切り落とすしかない。
失敗したら、再度フィルムを引き出して、揃えて、仮止めして・・・をエンドレスにさせられることになる。
実際そうなっていい加減こっちがキレたのは言うまでもない。
5. ゆるんだテープをリールに巻き取る
テープ修理が済んだら、仮止めマスキングを剥がす。
後はゆるんだテープを巻き取るだけ。
修復部分は必ず、使用済みリール側に巻く。
切り貼り部分を印字面に戻すと、また撚れや皺がでて絡んでしまう危険がある。
写真⇩ 鉛筆などをリール芯に挿して巻き取る

6. カートリッジを組み立てなおす
カートリッジの上部に“金属製のガイド部品”と新しいインクフィルムのリールを押さえる“金属製のワッシャ(シム)部品”がある。
取付け忘れの無いよう注意する。
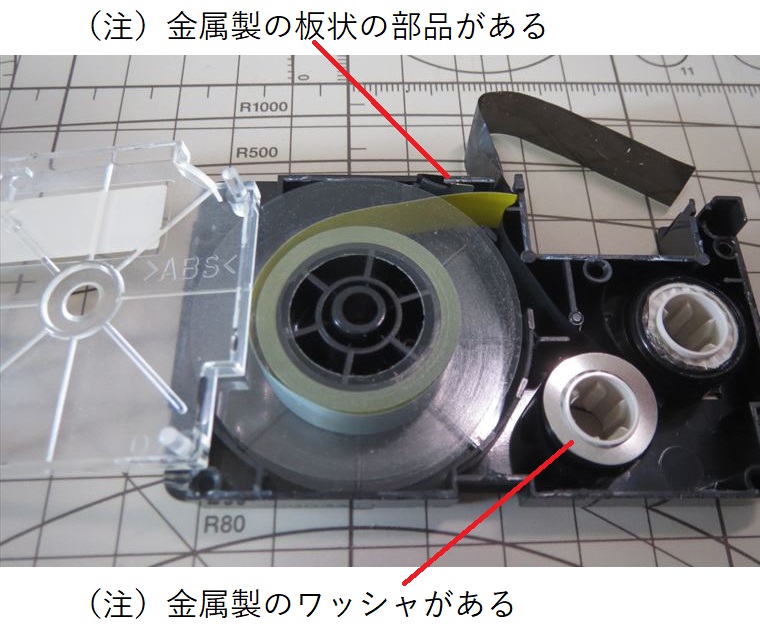
インクテープを挟み込まないように、慎重にケースを合わせる。

7.カートリッジケースの固定
カートリッジケースの分解時、接着剤を剥がしてしまっている。
また接着剤で固定してもいいが、もし染み出して内部を汚くしてしまっては困るので、再組み立ては透明テープで固定する方法にした。
何ヵ所かピっタリ貼って止めればたぶん大丈夫。
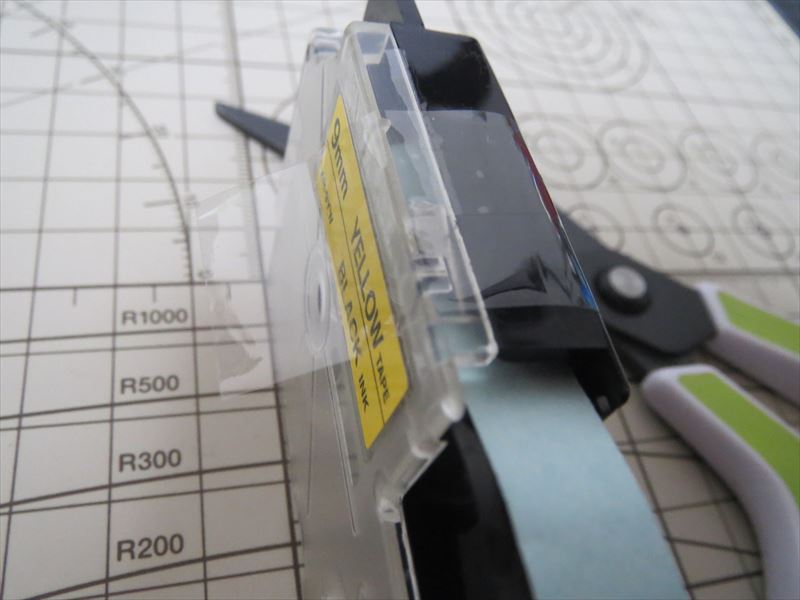
まとめ
ケース内部も小さな部品があるので、写真を撮りながら分解するのがお勧め。
この前のminiDVテープよりも薄い素材なので貼ってつなぐ場面では苦労した。
でもゆっくり慎重にやればなんとかなった。
テープ切れが起きやすいのは、ほぼ同じ理由、同じ場所。
つまり構造?素材?を改良してくれれば良いのだが。
メーカーさんには壊れにくい切れにくい製品を作ってほしいところ。
TEPRAラベルテープの修理(おまけ)
1 KINGJIMのラベルプリンタ
現在のmy工作室のメイン機はKINGJIMのTEPRAを使用中。
CASIOネームランドも使っていたが、最終的にはテプラになった。
ネームランドもテプラも何世代かを交代で使ってきて20年近になる。
その中、TEPRAで”テープ切れ”が起きたことはなかったことが現在メインにしている理由。
(運かも知れないけど)
ただテープ切れなくても、印字されないままラベルが出てきてしまうという別のトラブルがTEPRAであった。
(先代のSR3500Pでの症例)
これはプリンター本体の故障ではなく、ラベルカートリッジが古くなる=素材の劣化?で起きるらしい。
新しく買ったモノに交換したら再発しなくなった。
未開封カートリッジでも消費期限とかあるとは知らなかった。
写真⇩ メイン使いのSR5900P
2 TEPRA PRO
1.特徴
- 機械の設定からラベル文字編集までPC画面で操作できる
- 無線LAN対応
- 様々なフォントを使える
- 印字がすごく滑らかで 以前のようなカクカクな文字ではない
- 過去のラベルプリンターと比べると感動するキレイさ
- 印字が速い ※前機種に比べて
2.お気に入り機能
もう1つ便利な機能がオートカット。
この機能があるのは本当に便利。
※注)オートカット機能はCASIOネームランドにもあり
ラベル表面にだけカットが入りプリンターから出てくるので、
台紙からテープを剥がしやすい。
写真⇩ 2枚連続でラベルをプリントアウト
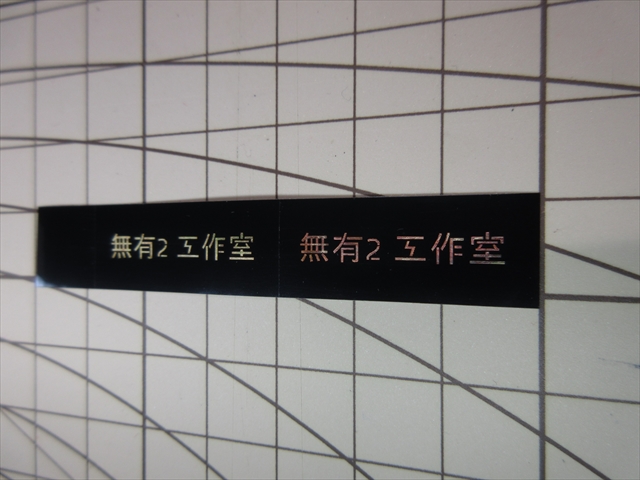
裏の剥離紙は切れていないが、
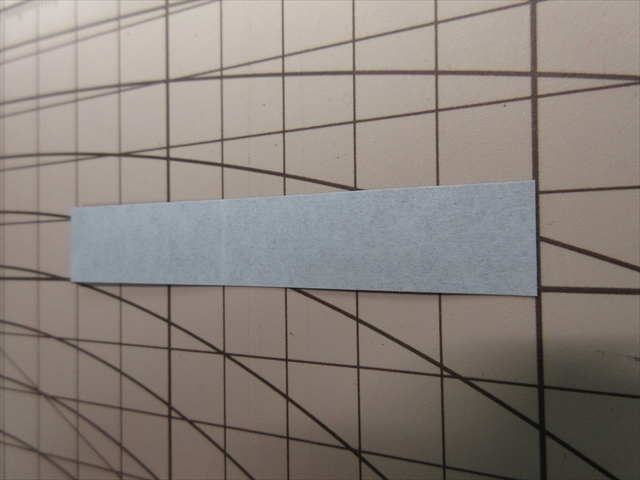
表のラベルテープの間にだけ 自動で“切れ目”が入り 剥がしやすくなっている。
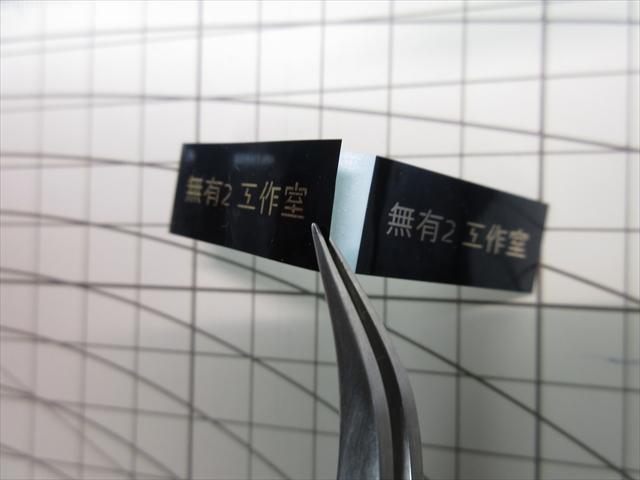
かなり おすすめ のラベルプリンターなのである。
3 TEPRAカートリッジの中身
テプラのカートリッジも、中身の構成はネームランドのカ-トリッジとほぼ同じ。

2か所あるクサビ形の固定爪を(-)ドライバー等でこじ開けやると分解できる。
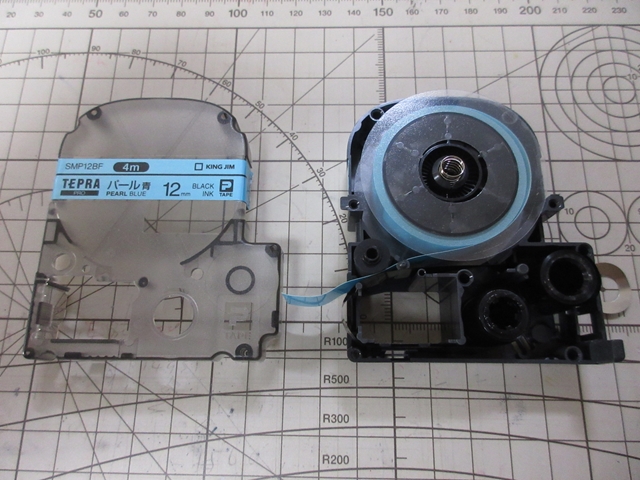
内部はこんな感じ。
もし切れた場合は、同じような要領でインクテープを繋ぎ直して修理できる。